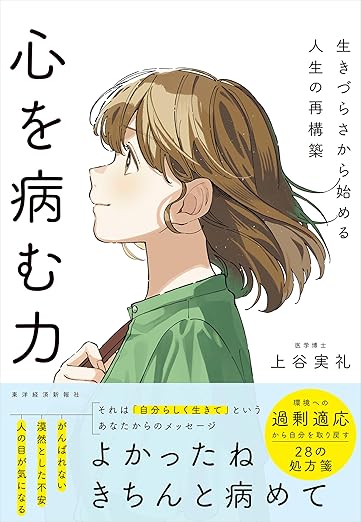人的資本経営、その“出発点”は自分を理解することから
先日、ある企業の経営メンバー・マネジメントクラスの皆さまを対象に、
「人間理解から始まる人的資本経営」というテーマで、
4時間の研修に登壇しました。
今回の研修の“裏テーマ”は、「自分を大切にする」。
人的資本経営や心理的安全性といった重要キーワードも、
その土台には“自分を知ること”があるという視点からお伝えしました。
30名弱の参加者の皆さんからは活発な質問をたくさんいただき、
「自分を整えることから、組織の安心感が生まれていく」
そんな体感と実感のある時間になりました。
心理的安全性は「文化」ではなく「神経の感覚」
冒頭では、「心理的安全性」という言葉を、神経学と心理学の両面から捉え直す時間を設けました。
「心理的安全性=文化や道徳的なマナー」ではなく、
「からだが“安全だ”と感じること」。
つまり、安全性は“アタマ”で理解するものではなく、“カラダ”で感じるものなのです。
たとえば職場で「感謝されない」と感じるとき、
それは単に感謝の言葉がないのではなく、
「自分が周囲とつながっている」という感覚が得られていないのかもしれません。
つながり=安全感。
そこに気づくことが、マネジメントの新たな視点になります。
自己理解から始める5つのステップ
研修では、サステナブルなマネジャーになるための5ステップとして、以下のプロセスを紹介しました:
- 自己受容
- 自己理解
- 他者受容
- 他者理解
- スキルの習得
上のステップだけを積み上げようとしてもうまくいきません。
“他者理解”や“マネジメントスキル”は、
自己理解があってこそ活かされるもの。
このプロセスを経ることで、
自分の内側に安全感が生まれ、
やがてそれがチームへと広がっていきます。
「マイルール」に気づいていますか?
「人に迷惑をかけてはいけない」と信じている人は多いと思います。
人に迷惑をかけないように心配りをすることは大切ですが、
「何を迷惑と感じるか」は人によって違います。
「人に迷惑をかけてはいけない」のような“考え”は無意識のマイルールなので
多くの人が自分の“マイルール”に気づいていません。
それはあまりに当たり前になりすぎているから。
感情は、マイルールに気づくきっかけになります。
「なぜこんなにイラッとするのか?」
「どうして気になるのか?」
そんな問いから、自分の内側とつながることができるのです。
「安全感」は言葉では伝えられない
安全感は、言葉で伝えるものではなく、
その人の“あり方”からにじみ出るもの。
まさに、相手に“駄々漏れて”いく感覚です。
たとえば、上司が部下に対して「なんでもっと早く言ってこなかったの?」と口にしたとします。
この言葉の背景には、上司自身が「安全を感じられていない」という状態があるのかもしれません。
その状態が、言葉や表情、声のトーンとなって、相手に伝わってしまうのです。
逆に、上司自身が「安全感を感じられている」心にゆとりがある状態であれば、
同じ場面でも「よく話してくれたね」と自然に声をかけることができるでしょう。
その一言とともに伝わる空気感が、部下にとっての安全感となっていくのです。
だからこそ、「何を言うか」だけでなく、「どんな自分でいるか」。
“あり方”が、心理的安全性の土台をつくる
――これはマネジメントにおいて、とても大切な視点です。
研修中に飛び交った問いと対話の数々
参加者の皆さまからも多くの質問をいただきました:
- 顔の表情と感情は、どちらが先?
- ストレス耐性は人によって違う?
- 若手は非言語コミュニケーションをどう感じているのか?
- 共感力には男女差があるのか?
- 価値観の違う人とどう協働するか?
それぞれの問いに対し、神経学や心理学の視点から考え、対話を通じて深めていきました。
多くの方が、「自分を知ることで、人との関わり方が変わる」そんな実感を持たれていたようです。
自分を大切にすることが、人的資本経営につながっていく
今回の研修では、「人的資本経営」や「心理的安全性」を、
“外側のスキル”ではなく、“内側のあり方”として捉え直す時間になりました。
それぞれの現場で、
部下の話に耳を傾ける、
言葉に気を配る、
そして何より“自分を整える”。
そんな積み重ねが、これからの経営やチームの土台をつくっていくと、あらためて感じました。
これからも、リーダー・マネジメントクラスの皆さんと一緒に、
“自分を大切にするマネジメント”を考え続けていけたらと思います。