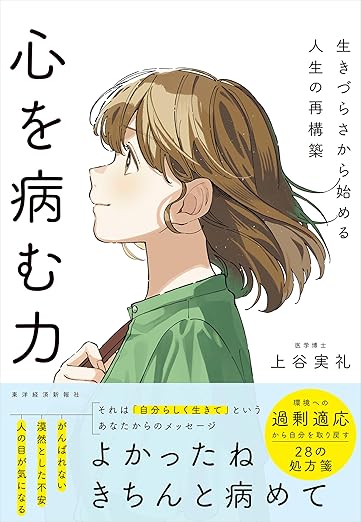X(旧Twitter)を賑わせた日経新聞の最近の記事をきっかけに、産業医・精神科医の先生が企画されたスペース(音声SNS)に参加する機会がありました。
◆日経新聞の記事はこちらです(※外部サイトへ移動します)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG2263R0S5A520C2000000
初めてのスペースはとても新鮮で楽しかったのですが、お祝いごとがあったためにお酒が入っていたこともあり(笑)、頭の中を整理して話せなかったという反省も。
そこで、今回のテーマを文章でじっくりまとめてみようと思います。
特に、スペースでのリスナーの方々から「ミレイ先生はベテランだし、説得するための、納得させるための面談技術が優れているから休職期間満了付近での復職支援でも揉めないんでしょ」というようなご意見が少なからずあり、これには正直、少しモヤモヤを感じています。
もちろん、手前味噌ながら、私の面談技術は決して低くないと自負しています。
実際、面談技術に関する書籍を執筆したり、研修を行ったりするだけでなく、普段の実務では人事担当者や保健師が面談に同席したり、オープンカウンセリングとして自身の面談を公開したりと、透明性を持って取り組んでおり、多くの方から「勉強になる」というお声をいただいています。
しかし、たとえ私の面談技術が高くても、「揉めない復職支援が、個人の面談スキルの問題に矮小化されてしまう」ことには大きな残念さを感じます。
なぜなら、スムーズな復職支援は、休職開始時、いや、平素のマネジメントの時点で既に決まっていると考えるからです。
面談技術は、あくまでも「枝葉」に過ぎません。普段からの土台づくりこそが、何よりも大切なのです。
さらに、日経の記事にある「産業医は精神科医であることが好ましい」という論調にも、ちょっとした「政治的」あるいは「ビジネス的」な匂いを感じ、モヤモヤが募ります。
私は長年産業医をしていますが、精神科医ではないことで困ったことは一度もありません.
精神科臨床の場で活動されている精神科ドクターには尊敬と感謝の気持ちでいっぱいですが、精神科医でなくとも、優れた産業医の先生方は大勢いらっしゃいます。
産業保健の現場においては、メンタル不調に関する知識と支援の経験、そしてたゆまぬ勉強を続ける意欲があれば、精神科医でなくても質の高い産業医業務は十分に提供できます。
今回のブログでは、日経の記事をきっかけにXで話題になった論点に触れつつ、私が考える「関係者の安心感と納得感を醸成する復職支援の土台」と「産業医の専門性」について、深掘りしてお伝えしたいと思います。
【本質】揉めない復職支援は「休職期間満了付近」で決まらない

Xでも話題になっていましたが、休職期間満了付近での復職支援は簡単ではありませんよね。
日経の記事にもあるように、ボタンの掛け違いが訴訟に発展する可能性もゼロではありません。
私自身、20年以上産業医として活動していますが、休職期間満了付近の復職支援で「大きく揉めた」経験はほとんどありません。
「全く揉めたことがない」とは言いません。
復職支援のプロセスで関係者の感情が波立つことはありますし、社員さんから「産業医の圧がすごかった」と評されることもあります(苦笑)。
それでも、なぜ大きく揉めることが少ないのか。
関係者の安心感と納得感を醸成する復職支援ができるのか。
これまでの経験を振り返り、その理由を10のポイントにまとめてみました。
これらは、単なる面談技術だけではない、「土台づくり」に関わる重要な要素です。
【実務】揉めない復職支援のための10の土台づくり

私が考える「揉めない復職支援」の土台は、以下の通りです。
1. 休職開始時の「面談」を重視する
休職に入るタイミングでの面談は非常に重要です。
その目的は多岐にわたります。
- 定点観測の基準把握: まったく知らない社員さんと復職面談で初めて会う状態だと、休職中の変化が分かりません。休職前や休職に入るタイミングの状態を知ることで、復職面談のときにどれぐらい回復したかを判断するための基準を把握できます。
- 休職経緯の把握: ハラスメントや上司・部下関係が原因となっているケースでは、社員さんの休職中に会社側でヒアリングを進められます。職制を通じて情報が上がってきても、ご本人の話を聞くと全く違って聞こえることはよくあります。
- 休職中の過ごし方・手続きの説明: 社員さんから「どんな風に過ごしたらいいですか?」と質問されることはよくあります。会社指定の復職診断書の書式を説明し、主治医に記入してもらうよう依頼します。復職後の有給休暇の取り扱いや傷病手当金などの手続きについては人事担当者から説明してもらいましょう。
- 産業医の存在認知: 「私が復職支援を担当します」と挨拶しておくことで、社員さんは安心感を抱きやすくなります。
2. 休職できる期間を明記した書面の交付
休職に入るタイミングで、休職できる期間が明記された書面を人事から社員さんに渡しておくことで復職支援のためのスケジュールが明確になります。
休職中の窓口担当者の連絡先、診断書提出のタイミング、復職後の有給休暇の取り扱い、傷病手当金など、休職者が知るべき情報を書面にして渡しておきましょう。
3. 休職中の「定期面談」の実施
休職期間満了間近になって、初めて会う社員さんから突然復職診断書が提出される状況は、トラブルの元になりやすいです。
このような事態を避けるため、可能な限り、休職中も定期的に産業医面談を行うようにしています。
これにより、社員さんの状態の変化を継続的に把握し、適切な支援に繋げられます。
4. マネジメント層への「休職対応フロー」の周知
人事担当者が知らない間にメンバーが休職し、いきなり復職診断書が提出される…ということがないよう、部下を持つマネジメント層に対し、部下が休職に入った際の対応フローを定期的に人事や産業医から説明しています。
これにより、早期発見・早期対応に繋がります。
5. 平素からの「情報共有とコミュニケーション」
前述4のようなことがないように、平素から現場のマネージャー層と人事・産業医の間で情報共有しやすい環境を整え、困ったときや判断に迷ったときにすぐに相談してもらえるようなコミュニケーションを密に取ることが重要です。
これは、産業保健における予防の観点からも非常に大切です。
6. 「休職者管理表」の作成と定期的な状況確認
休職者管理表を作成し、休職期間満了が近づいてから慌てることがないよう、定期的に人事と「この人どうなってる?」と状況確認を行うようにしています。
これにより、計画的な復職支援が可能になります。
7. 「緊急連絡先」の把握
残念ながら休職期間満了で自動退職となる際、ご本人よりもご家族から異議申し立てがあったり、連絡を取りたいのに社員さんと連絡が取れなくなるケースも稀にあります。
万が一のために、身元保証人やご本人以外の連絡先を会社側で把握しておくようにしています。
8. 主治医の診断書との向き合い方
日経の記事にもあるように、主治医が「復職可」と診断しても、産業医が「復職不可」と判断することは珍しくありません。
特に、休職期間満了付近の復職の場合、主治医が「復職不可」と判断することは自動退職を意味するため、主治医が社員さんの不利益になるような判断や、自身が患者さんから恨まれるリスクを負うような判断はされないだろう、と理解しています。
私が主治医の立場でも「復職可」の診断書を書くと思います。
人事担当者が「どうしてこの状態で(とても復職できるとは思えないのに)復職可の診断になるんだろう」と首をかしげることはよくありますが、私は前述のような背景を説明します。
主治医の先生方には大変申し訳ありませんが、産業医としては主治医の診断書を全て鵜呑みにすることは稀ですし、会社側も主治医の意見を丸飲みにはしません。
なぜなら、仕事を離れて日常生活ができるレベルと会社で仕事ができるレベルは異なっていて当然ですし、主治医が会社や仕事の状況を詳しく知る由もないからです。
また、人事権のない主治医の意見で配置や異動、評価がきまるようなことがあったら、会社としての組織運営に混乱をきたします。
「どうしてこの状態で(とても復職できるとは思えないのに)復職可の診断になるんだろう」という状態で復職可能の診断書が出ることに対して、「診断書は公文書なのに、公文書偽造になるのではないか!」と主治医に疑義を照会するようなやり方もあるのかもしれません。
しかし、主治医の先生方の事情も理解できますし、お忙しい臨床の先生方の手を煩わせることになるため、私は主治医に診療情報提供を求めるという選択は最低限にしています。
ごく稀に、休職期間満了のタイミングで主治医が「復職不可」と書いてこられるケースも経験しますが、それはよっぽどのケースに限られます。
とはいえ、現実的には、休職期間満了で自動退職の判断になるとトラブルのリスクが上がるので、基本的には一度は復職してもらうようにした方がいいのではないかなと思います。
「ちょっと難しいかな」と思うようなケースでは、結局、再休職になることが多いので、社員さんも納得された上で自主退職されていくことがほとんどです。
9. 産業医は「会社側」に立つという覚悟
産業医は中立の立場で支援すべき、と言われることがあります。
しかし、会社側と従業員側のどちらに立つかと問われるなら、私は迷わず会社側に立ちます。
これは、守秘義務を守らないとか、いわゆるブラック産業医のような振る舞いをするという意味ではありません。
昨日のスペースでも話題になりましたが、人事サイドから「この人には辞めてもらいたいので、先生からうまいこと言ってください」と頼まれることは現実的にはたまにあります。
もちろん、そのような依頼は断固として断りますし、雇用契約や就業規則に照らして伝えるべきことがあるなら人事から伝えてください、と明確に言います。
私が「会社側に立つ」というのは、雇用契約と就業規則の枠組みの中でしか従業員のサポートはできないからです。
どんなに個人的な心情として「この人をなんとかしてあげたい」と思っても、というより、そのように感じることはよくありますが、現実的には雇用契約の枠組みから離れて支援することはできません。
この線引きを明確にすることが、産業医としての中立性と専門性を保つ上で不可欠だと考えています。
10. 100%の共感とリスペクトをもって面談する

上記①〜⑨のような土台の上で、休職期間満了のタイミングであってもそうでなくても、私は社員さんと100%の共感とリスペクトをもって面談に臨んでいます。
面談では、カウンセリングのスキルも自然に総動員していると思います。相手の言葉の裏にある感情やニーズを理解しようと努め、傾聴し、時には沈黙も大切にします。無理に説得するような関わりはしません。
誠心誠意、向き合って対話をした結果、特段こちらが説得するような関わりをしなくても、社員さんご自身で退職の道を選択される方もいらっしゃいますし、一度復職はしてみたもののスムーズな就業が難しく、ご本人も納得して退職を選択されるということもあります。
その場合は、その人にとって最善の道が拓かれますようにと、祈るような想いで見送ります。
まとめ:安心感と納得感のある産業保健活動の鍵は「土台づくり」と「真摯な姿勢」

今回、日経新聞の記事とスペースでの議論をきっかけに、私なりの産業医としての信念と実践について、かなり長文でまとめてみました。
揉めない復職支援や産業保健活動の鍵は、単に「面談技術のスキルアップ」だけではありません。
それよりも、休職前からの一貫した対応、関係者間の密なコミュニケーション、そして産業医としての揺るぎないスタンスといった「土台づくり」が何よりも大切です。
そして、その土台の上で、社員さん一人ひとりに誠心誠意向き合い、尊敬の念をもって対話すること。
これこそが、紛争を未然に防ぎ、社員さんと会社双方にとって最善の道を見出すための、本質的な産業保健活動だと考えます。
この「休職と復職」というテーマは、2025年3月に開催した武神健之先生との出版記念対談セミナーでも深く掘り下げました。
武神先生のご著書『未来のキャリアを守る休職と復職の教科書』をベースに、私たち二人の産業医がそれぞれの視点から語り合った内容は、まさに休職・復職支援の教科書となるものです。
武神先生のご著書『未来のキャリアを守る休職と復職の教科書』はこちらです(※外部サイトへ移動します)

セミナーの様子は、下記のブログでご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
今回の記事が、日々の業務で奮闘されている若い産業医の先生方や産業保健師、人事労務担当者、マネジメント層の皆さんの参考になれば幸いです。
◆日経新聞の記事はこちらです(※外部サイトへ移動します)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG2263R0S5A520C2000000