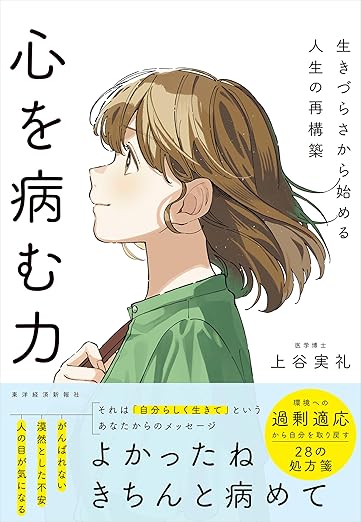日常に寄り添うラインケアを
先日、ある企業のマネジャークラスの皆さまを対象に、
「部下支援のためのマネジメント」をテーマとした1日研修に登壇いたしました。
オンラインでの開催ながら、50名近い方々にご参加いただき、活発な質疑と対話のやりとりから、現場での悩みや温度感がひしひしと伝わってくる時間になりました。
今回の研修では、受講された方々の「現場で“今”困っていること」について、皆さんと一緒に考える時間となりました。
「アドバイスも否定?」に広がる問い
印象的だったのは、
「アドバイスは否定になるのか?」
「でも、言わないと伝わらないし…」
という声が多く聞かれたことでした。
キャリア相談の事例も交えながらお伝えしたのは、
「相談するとすぐに道筋を作られてしまう」という声。
相談する人が必ずしも解決策を求めているとは限らず、
ただ話したいだけ、
ただ聴いてほしいだけ、
ということがあります。
こういう場合は、自分の考えを整理するために話を聴いてほしいのです。
アドバイスを求めているのか、それともただ聞いてほしいのか。
そう悩む時もありますよね。
その“違い”を確かめる問いかけそのものが、
部下の内省を深める機会になるのです。
シンプルですが、「話をしたいだけ?それとも解決したい?」と聞くことで、お互いのコミュニケーションの質がぐっと変わります。
境界線(バウンダリー)と共感のバランス
「部下からの相談に深入りするような質問をしたら、パワハラやセクハラになりはしないか」
という質問には、
切り口として「事例性・疾病性」を軸に持ちつつ、
KAPEサインを使った観察・介入の重要性をお伝えしました。
部下の課題をどこまで引き受けるのか?
どこまで寄り添い、どこで境界を引くのか?
こうした問いにこそ、管理職の“悩みのリアル”が詰まっています。
「相談にはのるけど、深追いしない」
「共感はするけど同情や同意はしない」
——支援のプロとして大切にしている視点を、現場のマネジャーにも等身大でお届けしました。
質疑から見えた「現場のもやもや」
研修では事前の想定を超えるほど、質疑応答が活発でした。
「質問することは貢献になる」
ということを研修でよくお伝えしています。
教えることが一番の成長につながりますので「教える側の成長貢献」という面や、
同じような疑問を持つ受講者の役に立ったり、
質問を通してノウハウ共有されたりという面があります。
職場のマネジメントには、
正解のない“もやもや”がつきものです。
でも、その“もやもや”を一緒に言語化して、
共有できるだけで、
少し前に進むことができるようになります。
オンラインという環境の中でも、
「ここは聞いていいんだ」
「この場では話していいんだ」
と思ってもらえるような空気がつくれたことは、
講師として何より嬉しいことでした。
日常に根づくマネジメントを目指して
対話のワークでは、
「話す側にもエネルギーがいる」
「話してくれるという行為そのものに思いを馳せてみよう」
という視点もお伝えしました。
何気ない1対1の対話こそが、
職場の心理的安全性の土台づくりの第一歩になります。
事務局の方からも
「今の現場に直結する内容だった」
「心理的安全性が場づくりのヒントになった」
というお声をいただきました。
今回の研修を通じて、日常のコミュニケーションがマネジメントの大切な“足場”になること、そして実践のヒントを得ていただけたら幸いです。