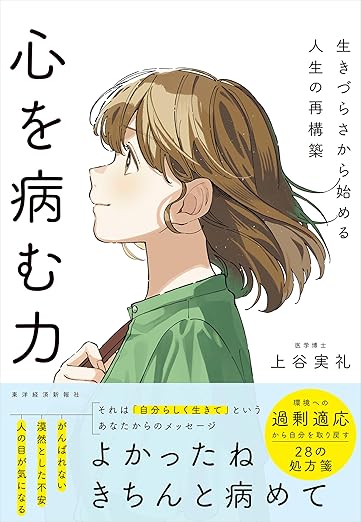人の行動の奥にある願い
「どうしてこの人はこんな行動をするのだろう?」
職場でも家庭でも、そんなふうに思ったことはありませんか。
先日、長野で開催された講演会「ポリヴェーガル理論を紐解き、いかす」にお招きいただき、登壇の機会をいただきました。
午前から午後にかけては師匠であるまひとさん(津田真人さん)によるレクチャーを聴講し、
そして15時からはまひとさん、ひきこもり支援に携わるあけみん(鈴木明美さん)とともに、
それぞれの現場でどのようにポリヴェーガル理論を活用しているかについて鼎談をしました。
従来の「二元論」の自律神経系では、ストレスは説明できてもトラウマは説明できません。
そのため、やる気が出ない、動けない、といった行動は「本人のやる気の問題」とされがちでした。
しかし、ポリヴェーガル理論の誕生により、それは意思や性格ではなく、
神経レベルの自然な身体反応だということが説明できるようになりました。
「この反応は何を伝えようとしているのだろう?」
そんな視点が、産業保健やセラピーなどの対人支援の場でも、そして日常の人間関係の中でも、大切なのだと改めて感じました。
問題行動とレッテルを貼ってしまいそうな行動の奥には、どんな願いや背景があるのでしょうか。
今回の講演と鼎談は、そのようなまなざしを深めてくれる時間でした。
ポリヴェーガル理論の視点から ― 3つの神経が教えてくれること
まひとさんの講義はこれまでも何度も聴いてきましたが、聴くたびに新しい学びがあります。
ポリヴェーガル理論は、1994年にスティーブン・ポージェス博士が提唱した新しい自律神経系の理論です。
副交感神経の8割を占める迷走神経が2つに分かれることから、自律神経系の反応を次の三元論で説明します。
- 腹側迷走神経複合体(向社会的行動)
- 交感神経系(「闘うか逃げるか」に代表される能動的対処)
- 背側迷走神経複合体(「フリーズ/シャットダウン」に代表される受動的対処)
交感神経系や背側迷走神経複合体の働きによって病態や問題行動を理解できるようになり、
腹側迷走神経複合体の働きは「どう健康を回復していくか」の鍵となります。
ポリヴェーガル理論の視点から見ると、
健康とは、腹側迷走神経複合体・交感神経系・背側迷走神経複合体の3つの状態を柔軟に行き来できる状態
と言えます。
一見「いい」とされる腹側迷走神経複合体でさえ、固定されてしまえば病的と言えるのです。
危険な状況においては、危険に応じて交感神経系を活性化できることが健康な状態なのです。
そして腹側迷走神経複合体は、人とのつながりを生み出す神経でもあります。
上司と部下、カウンセラーとクライエント、医師と患者、教師と生徒、養育者と子ども――。
人が成長や回復していくときには、必ず「関係性の質」が深くかかわります。
この視点を持つと、私たちは目の前の相手を「行動」ではなく「願い」で見ることができます。
動けないのは、願いが叶わなかったからかもしれません。
そして多くの場合、その願いは「誰かとつながりたい」ということなのかもしれません。
鼎談 ― 3つのフィールドから
鼎談には3人が登壇しました。
- あけみん(鈴木明美さん):ひきこもりの若者支援の立場から
- まひとさん(津田真人さん):カウンセリングの立場から(講義も担当)
- 私:産業保健の立場から
まったく異なるフィールドで活動しているからこそ、それぞれの現場での活かし方を共有し、学び合うことができました。
ひきこもり支援の立場から
少年院でのカウンセリングでは、多くの少年が防衛的な状態からのスタートとなるとのことでした。
「どう関係を築くか」はスキルではなく、カウンセラーのあり方そのものが試される。
初回面談での少年との関係の築き方、カウンセリングを続ける中での関係性と少年たちの変化。
あけみんが語る1つ1つのエピソードに、心が震えました。
カウンセリングの立場から
「自分のメンテナンスは?」という質問に対し、まひとさんが答えられたことの1つは、
「食べ過ぎないこと・寝不足にならないこと」。
最も原初的な欲求の充足こそが、すべての土台になるという言葉が印象的でした。
そしてまひとさんのこの言葉が心に残っています。
この人生で手に入らなかったものは何か。
それが手に入らなくて苦しんでいる。
その人が何を手にしたかったのかにチューニングしていく。
人を見るまなざしが一気に深まる瞬間でした。
産業保健の立場から
私は産業医の立場から、
- 個人
- 上司・人事
- 組織
- 支援者
という4つの視点で話をしました。
休職や復職期にいる人は、自分が思うように動けないことを責めがちです。
そのとき、相談者自身に「これは意思や根性の問題ではなく神経の反応だ」と理論的に説明すると、できない自分を責めることから解放され、安心して治療に専念したり、他者を頼ったりすることができるようになります。
「やる気がない」とレッテルを貼るのではなく、
その人の身体が何を必要としているのか、
そしてその奥にある“生きようとする力”を見つめること。
それが産業保健でポリヴェーガル理論を活かすときの最大の意義だと感じます。
今回、このような貴重な機会を作ってくださった学びの仲間であり、ゲシュタルト療法の先輩でもあるDream Seed (心と身体にかかわる専門職のサポート)の三井洋子さんに心から感謝申し上げます。
気づきと学び
今回の講演と鼎談を通して、改めて感じたのは――
- 行動をジャッジするのではなく、その奥にある願いに目を向けること
- 「動けない」「やる気がない」も神経系の自然な反応であること
- 医師や支援者である前に、一人の人間として、この視点に自分自身が支えられていること
「ありのままの自分で人とつながり、社会の中で自分らしく生きる」活動を、これからも続けていこうと思いました。
まとめ ― 今日からできること
ポリヴェーガル理論を知ると、「行動を直す」ではなく「人を理解する」というまなざしを持てるようになります。
あなた自身にも、安心してつながれる場所や人はありますか?
対人支援職は目の前の人のことを大切にしようとするあまり、自分を大切にすることを見落としがちです。
まず自分を大切にしてこそ、自己犠牲にならずに他者を大切にできるようになります。
まずはシンプルに、
• 食べる
• 眠る
という基本を大切にしてみてはいかがでしょうか。
そして一日の終わりに「今日もよくがんばったね」と自分に声をかける。
そんな小さなセルフケアから、安心の感覚が育っていきます。