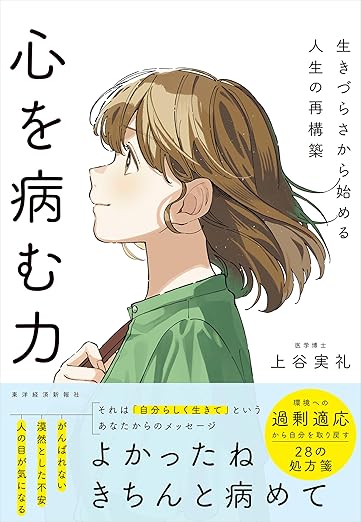AI時代に改めて問われる「安全」とは?
生成AIが急速に広がる今、私たちの働き方や人間関係は大きな変化を迎えています。
こうした時代だからこそ、職場における「心理的安全性」はますます重要になってきます。
2023年8月に開催した「職場の心理的安全性とポリヴェーガル理論」セミナーの続編として、
今回は「AI時代の職場の心理的安全性とポリヴェーガル理論」と題し、
ポリヴェーガル理論の第一人者・津田真人先生をお招きし、
講義と私・上谷実礼の対談によるセミナーを開催しました。
AIと人間の役割、
身体性と関係性、
そして「安全」の本質。
このセミナーを通して、「AIは便利だけど、人間はどう在るのか?」という根源的な問いに向き合うことが、今の時代に避けて通れないテーマだと実感しました。
セミナーで印象に残ったキーワード
- 関係性
- 大きすぎるシステムの中で感じる無力感
- トラウマの時代
- 愚かな神としてのAI
- 人間は出来損ないのAI
- 経済学と生理学を接合せよ
「なぜ生きるのか」
「何のために生きるのか」
「人間とは何か」
「命とは何か」
このようなすぐに答えが出ない種類の問いに向き合うのには時間がかかります。
だからこそ、出来損ないのAIとしてではなく「人間」として生きていくために、
考え続けること自体が意味のあるテーマだと感じました。
心理的安全性って、結局何が大事なのか?
心理的安全性とは、
チームのメンバーが「人間関係のリスク」を恐れずに、
意見を出したり失敗を報告したりできる状態のことです。
だとすれば、
AIに頼ることでリスクそのものを取り除いてしまう解決策は、
問題の核心を見逃してしまいます。
つまり、人間同士が信頼関係を築くために不可欠な「リスクを乗り越える経験」を奪ってしまうのです。
また、タイパと生産性至上主義のもとに生活に入り込むAIと適度な距離感を保てなければ、
考える力や判断する力、表現する力はじわじわと低下していきます。
気づいたときには「AI骨粗鬆症」になっているかもしれません。
そして、
AIにリスクを請け負わせることで、人間関係そのものが希薄になっていき、
ここでも「人間関係におけるAI骨粗鬆症」を招く危うさがあります。
ポリヴェーガル理論が照らす「安全感」
ポリヴェーガル理論では、自律神経系の働きを進化の過程から、階層的3元論として説明します。
- 腹側迷走神経複合体:安全な状況における向社会的行動
- 交感神経系:闘争か逃走かに代表される、危険な状況における能動的対処行動
- 背側迷走神経複合体:凍りつき・シャットダウンに代表される、生の脅威における受動的対処行動
「心理的安全性」とは、単に制度やルールの問題ではなく
からだが安全を感じられるかどうかに深く関わっています。
「身体のない脳」であり、私たちを欺く“愚かな神”であるAI
AIはすべてを知っているように振る舞いますが、
実際にはネット上の情報を寄せ集めているに過ぎません。
利害や「自分の都合」をもたないため、
完全に中立で客観的な相談相手のように見え、
その幻想に私たちは惹きつけられます。
しかし、AIは「身体をもたない脳」であり、
物理的な現実に根差した「自分」という視点を持ちません。
そのAIと、身体をもつ私たち人間はどう付き合っていくのか。
私たちは、生身の人間——本当の他者——を必要とせず、
「出来損ない」のAIとして生きていくのか。
それとも「人間」として生きていくのか。
今まさに、その選択を迫られているのかもしれません。
参加者の声(抜粋)
セミナー後には、多くの感想をいただきました。
掲載可としてくださった方の感想から、一部をご紹介します。
- 出来損ないのAIではなく、人間として生きていきこうと決意しました。
- 自分自身の身体の再生産に気づくことが、自然環境における再生産への気づきにつながるという視点にもハッとしました。
身体性と環境が深く結びついているという理解は、今後の働き方や社会の在り方を考える上で大きな指針になると感じました。 - AIは、「自分」という視点がないというのが、身体がないという解説ですごく納得できた。
- 「AI的でない人間ほど差別され排除されていきはしないだろうか?」という言葉に、
ひきこもりの若者達の顔が浮かんだ。 - 身体の感覚がなくなればなくなるほどポンコツなAI化してしまうので、
身体の感覚に敏感でありたいと思いました。 - 「話し相手や相談相手にAIを求める私たちは、もうすでに生身の人間を求めていないのではないか」というまひとさんの言葉にドキリとしました。
参加者の声からは、AIの便利さを超えて「人間らしさ」を改めて考え直すきっかけを持ち帰ってくださったことが伝わってきます。
まとめ:便利さと豊かさの間で、私たちは何を問われているのか
AIは仕事を奪う脅威と感じられていますが、と同時に、人間が人間らしく生きるための“鏡”でもあります。
今回のセミナーを通じて考えが深まったのは、
「富の生産」を至上命題とするシステムがもたらす便利さと、
私たちの身体に根ざした豊かさとの間にある根本的な対立でした。
そして私たちは今、その重大な選択を迫られています。
AIの効率や快適さに思考を明け渡すのか。
それとも、人間であることの面倒で非効率だが豊かなプロセスを取り戻すのか。
効率という名の幻想に流される前に、
“身体”という現実を取り戻し、そこから思考できるかどうか。
セミナーを通じて私自身も、
「安全安心を感じられる身体」「人と共に考え続ける姿勢」こそが、
これからの時代を支える力だと再確認しました。
ご参加くださった皆さま、本当にありがとうございました。