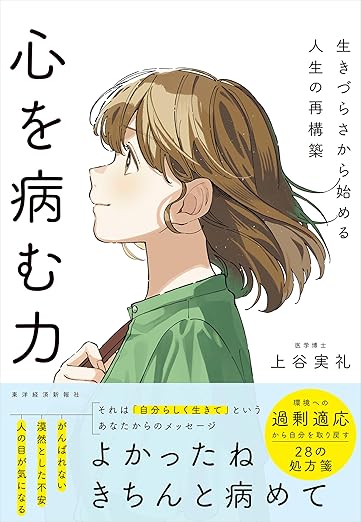支援職が集う、熱気あふれる“フェス”のような学会
先日、仙台で開催された日本産業衛生学会に参加してきました。
この学会は医師だけでなく、看護職、保健師、産業カウンセラー、人事パーソンなど、さまざまな職種の方が集う場。
年々参加者が増えており、今年はなんと6,000人規模。
会場の熱気は、まるでフェスのようでした。
今回の学会をきっかけにご縁をいただき、夏に開催される別の学会の教育講演の演者として呼んでいただけることになりました。
ポリヴェーガル理論について、産業保健スタッフの皆さんにお伝えさせていただきます。
初の自由集会「支援職のセルフケア研修会」を開催
今回の仙台で、初めての自由集会の企画・開催にもチャレンジしました。
テーマは、「支援職に必要なバウンダリー(境界線)」。
自由集会の場には、雨の中にもかかわらず50名近くの方がご参加くださいました。
レクチャーだけでなく、ダイアローグやペアワークも交え、温かな空気のなかで進めることができました。
涙ぐみながら聴いてくださる方もいて、
「皆、それぞれに抱えながら支援職として頑張っているんだなぁ」と、
私の心も動かされる時間でした。
バウンダリー(境界線)とは?
今回の自由集会では、私が執筆を担当した雑誌『産業保健と看護 2025年3号』の特集記事をベースに、以下のようなことをお話ししました。
- 境界線とは何か、その定義と役割
- 健全な境界線と、不健全な境界線の違い
- 支援職にとっての境界線とは?
- 健全な境界線を保つためのスキルとマインドとは
「バウンダリー」は、見えないけれど、確かに存在する“自他の境界”。
目に見えるドアや塀のような境界もあれば、心のなかにある、言葉にならない境界もあります。
支援職にとって、このバウンダリーの感覚はとても大切。
関わりすぎず、
離れすぎず、
「自分をすり減らさずに関わる」ための軸でもあります。
📰雑誌はこちら 👉 産業保健と看護 2025年3号(特集)
🎥紹介動画はこちら 👉 YouTubeでチェック
サステナブルな支援職を目指して
いっときであれば、自己犠牲的に働くこともできるかもしれません。
でも、それは続きません。
「支援職」という仕事を、持続可能にしていくためには?
それを問い直す時間を、今回の集会では参加者のみなさんと一緒に過ごすことができました。
この学会、そして自由集会は、仲間たちと一緒に企画・運営したもの。
「来年もまたやろう!」という声がすでにあがっていて、今から楽しみです。
最後に――支援職のみなさんへ
今、支援の現場に立つあなたが、
もし少しでも疲れを感じていたら、
「どこまで関わり、どこからは引いてもいいのか」
そんな“境界線”を見直すタイミングかもしれません。
自分をすり減らす支援ではなく、
「自分を大切にすること」も支援のひとつ。
これからも、サステナブルな支援職として生きるためのヒントを、少しずつお届けしていきます🍀