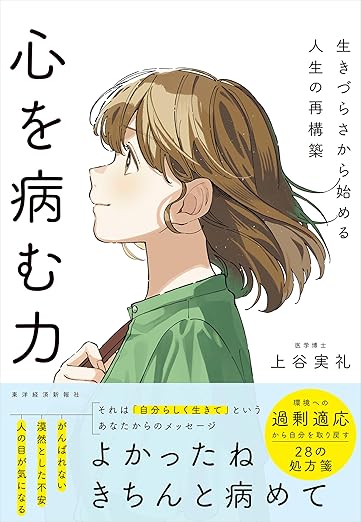お盆期間の最終日に日本ゲシュタルト療法学会主催の研修会に参加しました。
NY州の精神分析家・富樫公一先生が「臨床家の可傷性と当事者性」というテーマでお話しくださいました。
心が動く話を聞くと、学びながら涙が出てくることがあるのですが、この研修もまさにそういうお話でした。
専門家や治療家であるという立場が持つ可傷性については常日頃考えていることですが、この研修では、専門性や立場がなくても、人と人が分離した存在として出会うときには可傷性を持つのだ、という視点を改めて教えていただきました。
治療家が患者を傷つけることもあれば、患者との関係性が治療家を傷つけることもあります。
お話の中では、専門家としての倫理的行動と、専門家である以前に人としてどのように患者に出会うのかという「精神分析の倫理的転回」について触れられました。
私自身のことで言うと、クライエントと多重関係にならないように気を付けることと、自分自身であることの境界についていつも悩みます。専門性を守る選択をすることも、自分としてふるまうことを選択することもありますが、自分自身としてふるまうよりも専門性を守る選択をしたときには自分が傷つくような、人として大切なことが損なわれるような感覚があることに気づいています。
分断された世界を生きる私たち
この世を生きる人間どうしの出会いの根底には傷つけ、傷つけられる可能性がどうしようもなく存在しています。
世界は、被害者-加害者、善-悪、当事者-専門家などのように名づけられることで分断されます。
富樫先生の
名づけにより分断されている世界のあり方そのものがトラウマだ
という話には深く共感しました。
「共感する」、「理解する」という姿勢は、「あなた」と「わたし」は別の存在であるという前提があります。この分離があるからこそ「共感しよう」「理解しよう」という姿勢が生まれるのです。
「あなた」は「私」であったかもしれない
ここで大切になるのが「当事者性」です。
私が私であり、目の前の人がその人であることは偶然にしか過ぎません。
現代の日本で両親のもとに生まれたことも、単なる偶然にしかすぎないのです。それなのに、人々やモノは、偶然に割り当てられたそれぞれのあり方で名づけられます。そして、そこから分断が生まれます。
「隣人はもしかしたら私であったかもしれない」という自覚。
「被害者は、加害者は、私であったかもしれない」という自覚。
これが富樫先生の言う「当事者性」です。
世界に分断が生まれる以前、分断が誕生する瞬間「ゼロのモーメント」に立ち返り、身を委ねると、目の前の人が他者ではなく、本来的に分断された自分であった可能性に自覚的になります。
まさしく、わたしはあなたであり、あなたはわたしなのです。
この瞬間の宇宙のありようが偶然の積み重ねならば、私たちにとって、目の前のあなたや目の前の患者は他人ではありません。別の偶然があれば、いつでも自分がその人であったかもしれないのです。
富樫先生はそのようには説明されませんでしたが、分断が生まれる以前の世界をイメージするとワンネスとか縁起のようなことかなと私なりに理解しました。
目の前の人が自分だったかもしれないとしたら、「共感する」とか「理解する」といった態度とは、また異なるまなざしが生まれるでしょう。
富樫先生のお話を聞いて、支援職として、セラピストとして、意識が拡がり、視座が変わるような感じがしています。
ご案内
● 富樫先生のご著書↓↓↓
● 富樫先生の記事掲載サイト↓↓↓
● 今回の日本ゲシュタルト療法学会主催の研修会イベント案内